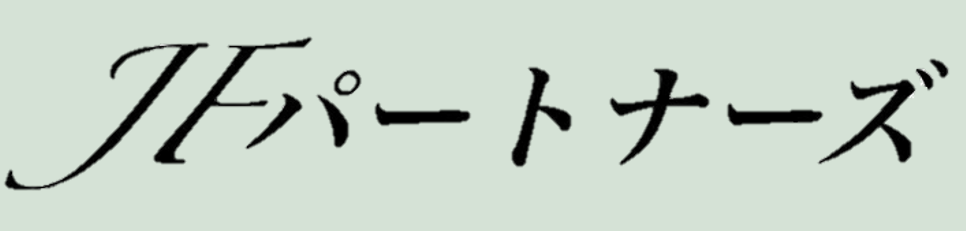予防接種健康被害救済制度の審査請求の問題点
私が支援しているコロナワクチン接種により著しく健康被害が生じた方は、予防接種健康被害救済制度と他制度の各種請求も行われました。予防接種健康被害救済制度の医療費、医療手当は認定され、合わせて障害厚生年金や障害者手帳(精神)についても認められています。 しかし、予防接種健康被害救済制度の障害年金のみ不支給となり、住所地の知事に対して審査請求をされました。私は、その経過をつぶさに見てきましたが、どう考えても制度上大きな問題があるこの制度について解説いたします。
審査請求のおかしな点
予防接種法にもとづくこの救済制度は、厚生労働省のホームページの概要にも記載されている通り「予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるもので、過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するもの。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われ、申請に必要となる手続き等については、住民票を登録する市町村にご相談ください。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。」とされています。
すでに矛盾がある文書になっているのですが、この制度は健康被害にあわれた方は、お住いの市町村に申請し、厚生労働大臣が因果関係を認めたら、市町村が支給決定するという仕組みです。大臣が認めたら市町村が支給決定する?それは大臣が支給決定しているのではないのでしょうか?という疑問が生じます。実務としてはその通りで、市町村長がハンコを押してご本人に「不支給としましたので出せません」と通知はしますが、不支給決定をしたのは厚生労働大臣です。一般的な市町村への法定受託事務は、その決定も含め法の基準に基づいて、国が市町村長に委託するものです。しかしこの制度は、基準がない中で国が決めたことを、体裁は市町村長が決定したように見せかけて、国民に通知します。 そして、この制度の審査請求(不服申し立て)は、行政不服審査法にもとづき、処分庁(市町村)の上級官庁である都道府県知事に対して何とかしてくれという不服を申し立てる仕組みになっています。実際は大臣が決めたことについて、下級官庁の都道府県知事に何とかしてくれと言っているのです。
審査請求の内容は
当然、都道府県の審査請求された側が、大臣に歯向かう訳はありません。冒頭書いたように厚生労働大臣は決定するにあたって、厚生労働省が雇う医師からなる「疾病・障害認定審査会」に医学的な見解を聞きます。医師達は「現在の医学的な知見から考えると、コロナの予防接種で出たそんな症状なら、時期的にもっと早く発症するはずだ」などの理由で認めない場合が多くあります。医師達の結論がそうであれば、大臣は単にその結果通り「否認」ですと市町村に連絡し、市町村は「認められない」と被害者に通知するのです。ですが被害者は「症状の出現は人によって差があり、私の主治医は発症が遅いことはないと言っているし、海外の論文にもそう書いてある」という様な反論をしたくなります。普通の不服申し立てであれば、「それでは厚生労働省で審査した医師達、または別の医師に聞いてみましょう」というのが適切なやり方であると思うのです。ところが、この審査請求で都道府県は一切このような手段をとりません。都道府県の中の事務方だけで、医師には全く聞きもせず「市町村の行った事務手続きの手順には全く問題が無かったから、結論は変えません」という事務手続きの審査しか行っていないのです。
障害年金の否認理由
今回の私が立ち会った障害年金の否認は、もっと理屈が通らない事になっています。この方の否認理由は「障害の状態が固定していないから」というものでした。ところが障害年金受給要件に、障害が固定していなければならないという事は、何処にも規定がありません。しかも、予防接種法施行令第15条に「障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。」という条文があり、障害の状態が変わって良くなったら、年金は支給しませんよ、とわざわざ書いてあります。つまり、法文では、障害状態が良くなった場合の事を、逆に言うと障害固定していない場合の事を想定した決まりが書かれているのです。それにもかかわらず厚生労働省の審査会の医師達はこの条文は無視して、今は障害の状態が固定していないからダメと言うのです。
この理屈で言えば、今後悪化する可能性があっても出さないし、改善の見込みが少しでもあったら出さないという事になります。今後悪化して亡くなる可能性がある方には支給しないということになり、もはや障害年金は救済制度ではありません。厚生労働省のどこかで、このように勝手なローカルルールが作り出され、何の問題も無いかの如く、このやり方が定着されています。
また、予防接種法第15条に「予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき給付を行う」と書いてあります。予防接種を受けたことによるのか否かを、厚生労働省の審査会は審査する場であって、因果関係を医学的に議論するものだと書いてあります。それにも関わらず、因果関係が明らかな方についても、障害が固定しているか否かを判定させて、あたかも医学的に認められないという体裁をとっているのです。
法や施行規則、審査基準、どこにも記載がない中でのルール
国民年金や厚生年金の障害年金では、障害認定日として、年金支給の障害の状態を定める日を決めています。その障害の原因となった病気やけがについての初診日から、1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気や怪我が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。これは、身体が障害の状態になった時でも、一過性ですぐ直るかも知れない場合もあることから、初診日から1年半経過して、身体の障害状態が一定のものであれば(又は1年半以内で怪我は完治したが障害が残ったら)その方には年金を支給するという考え方です。
この国民年金・厚生年金と同じ「1年半ルール」で障害年金を支給する制度は他にもあります。それは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度です。これは、予防接種健康被害救済制度と平行した、予防接種等を含む医薬品被害者を救済する制度です。
さらに同じ予防接種で、2009年公布された「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法」では、新型インフルエンザの予防接種を実施したことによる健康被害が発生した場合の障害年金も「1年半ルール」を適用しています。
こうなると、予防接種健康被害救済制度は、何故「1年半ルール」を使わないのか、その理由が全く不明です。通常法律に基づき、国民に対し国が行った予防接種の健康被害に、責任をもって救済すると言うのなら、支給する基準として障害が固定していなければならないという、その理由を明らかにしなければならないと思います。現実は、市町村や都道府県の職員すらその理由を聞かされず、厚労省内の勝手な独自ルールで、給付範囲を絞っているとしか思えません。
制度の改善に向け
知り合いの弁護士さんから伺いました。「法律家からするとルールが言語化され公開がなされていない状態は「人の支配」であり、「法の支配」とはいえない。これはこの救済制度の大きな欠陥であり、改善されなければならない」と仰られていました。
そして行政手続法第5条(審査基準)には、このように書いてあります。 1 行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない 厚生労働省は、行政手続法も無視した運用をしています。
厚生労働省のホームページには、認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われている。と堂々と記載されています。
言っていることとやっていることが違い過ぎる行為であり、手続きがブラックボックスとなっている現状です。こうした中での審査請求は、被害者として極めて困難なものとなっています。
多くの問題を抱えているこの制度について、近く厚労省との意見交換をする予定です。また、来年1月から行政書士法が改正され、特定行政書士として審査請求に更に深く関与できるようになります。私はこの大きな社会的問題については、被害者を中心とする広いネットワークが築かれ、被害の実態を厚生労働省にまじめに調査させ、救済制度の改善を早急に行いながら、何故このような事態に陥ったのか、再発防止策等について予防接種政策の根本から真摯に議論されることが必要であると痛感しています。